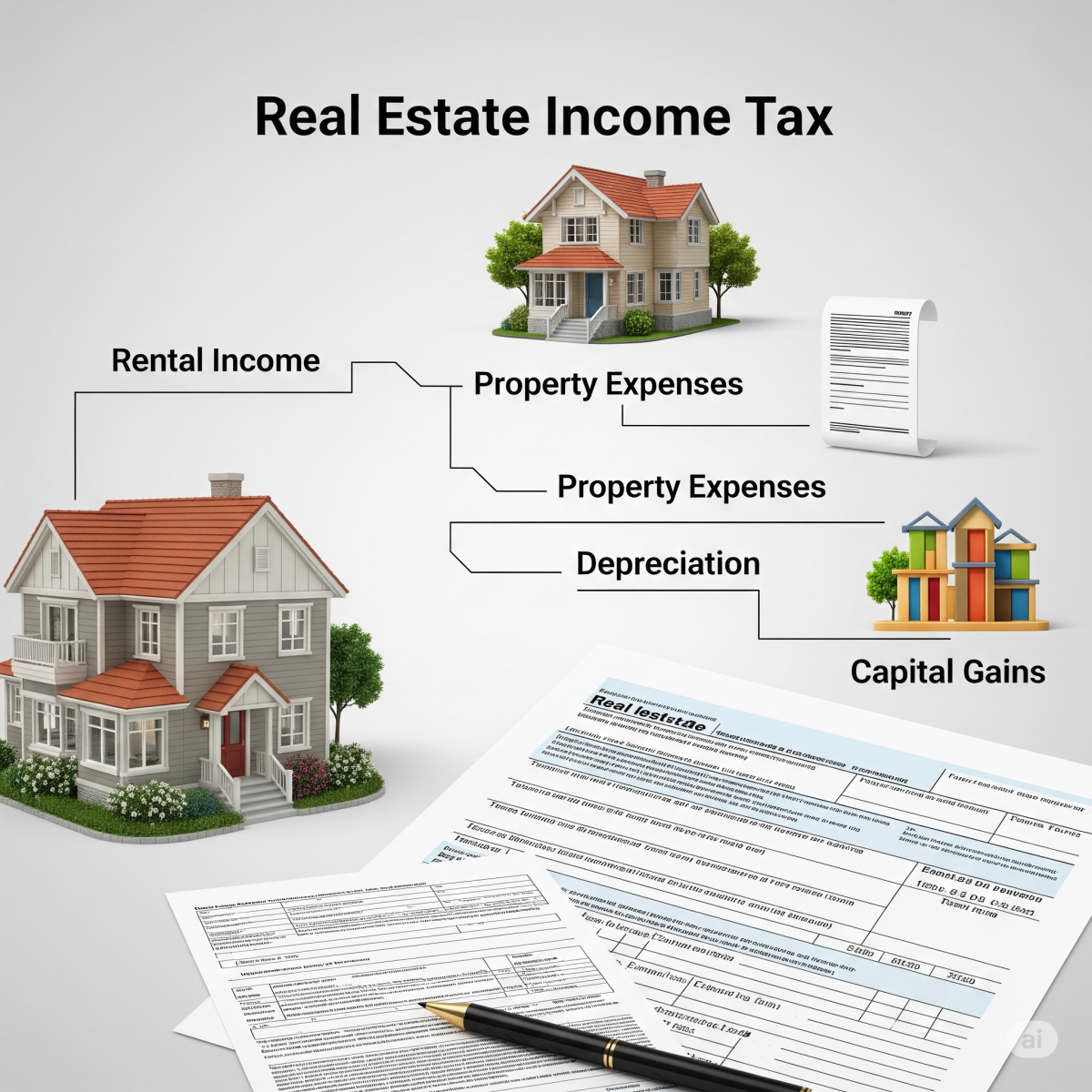こんにちは! 長らくお休みを頂いておりましたが、本日から再開いたします。また読んでいただければ幸いです。
今回は「三為契約」という言葉についてご紹介します。
不動産投資の現場で時々耳にすることがある「三為契約(さんためけいやく)」という言葉。正式には「第三者のためにする契約」と呼ばれ、通常の売買契約とは異なる特殊な契約形態のことをいいます。
名前を聞いたことはあっても、「どんな仕組み?」「メリットはあるの?」「リスクは?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
⚪︎三為契約の基本的な仕組み
三為契約とは、「売買契約によって発生する権利(所有権移転など)を、契約当事者でない第三者に直接帰属させる契約」のことです。
売主(Aさん):不動産を売りたい人
買主(Bさん):Aから不動産を買い、Cに売る人(中間者)
第三取得者(Cさん):実際に不動産を手に入れる人
通常の取引では「A→B→C」と所有権が移転しますが、三為契約では、契約上はAとBが契約しつつも、登記はAから直接Cへ移ります。つまりBは間に入るだけで登記には登場せず、所有権も形式上は一度も持ちません。この形式は「中間省略登記」とも呼ばれます。
⚪︎なぜ三為契約を使うの?
三為契約には次のようなメリットがあります。
1. 登記や税金のコスト削減
通常の転売では登記手続きが2回必要で、登記費用や登録免許税も2回分かかります。しかし三為契約ならA→Cへの1回の登記で済むため、費用を大幅に抑えられます。
また、Bが不動産を自分名義で登記しないため、不動産取得税も発生しません。
2. スピーディーな転売が可能
不動産業者などが物件を仕入れてすぐに他の買い手に売却する際、自己資金や時間を節約できるため、取引を効率よく進められます。
3. 中間者にとっての事業チャンス
Bさんのような投資家や仲介業者にとっては、リスクを抑えつつ利益を得られるチャンスです。資金を多く持たない業者でも、大きな取引ができる可能性があります。
⚪︎注意すべき点
便利な三為契約ですが、当然注意しなければならない部分もあります。
1. 契約関係が複雑
三者が関わることで、トラブル時に誰が責任を負うのかが不明確になりがちです。瑕疵が見つかった場合、損害賠償の責任範囲も複雑になります。
2. 契約解除やトラブルの連鎖
たとえば、Cさんが契約をキャンセルした場合、BがAとの契約も解除せざるを得なくなる可能性があります。結果的にAも買い手を失い、Bは利益を失うという事態に。
3. 融資が通りにくくなることも
金融機関の中には、三為契約に対して慎重な姿勢を取るところもあります。特に、転売益目的と判断された場合、ローン審査が厳しくなる可能性があります。
…などがありますので、都度問い合わせつつ検討していきましょう。
⚪︎三為契約を利用する際の注意点
三為契約はメリットが大きい一方、契約内容や関係者の信頼性が非常に重要になります。以下の点を意識しましょう。
専門家に相談する:契約前に、弁護士や司法書士、不動産専門家に必ず相談しましょう。
契約書を細かくチェック:それぞれの立場での責任範囲や解除条件などを明確にすることが重要です。
情報共有をしっかりと:三者で誤解がないよう、取引の全体像を共有することがトラブル防止に繋がります。
融資の事前確認:Cがローンを使う場合、金融機関と事前に三為契約の可否を確認しておきましょう。
三為契約は、不動産売買の効率化やコスト削減に非常に有効な手法ですが、その分契約は複雑で、関係者間の信頼や情報の透明性が欠かせません。
特に中間に入る人(Bさん)は、しっかりと知識を持ち、リスクを把握して行動する必要があります。「儲かるから」と安易に飛びつくのではなく、専門家と連携し、慎重に進めることが成功の鍵です。不動産投資を始める方は、ぜひ三為契約の仕組みとリスクを正しく理解しておきましょう。
収益不動産売買のご検討、管理・経営でお悩みごとがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください!(^_−)−☆