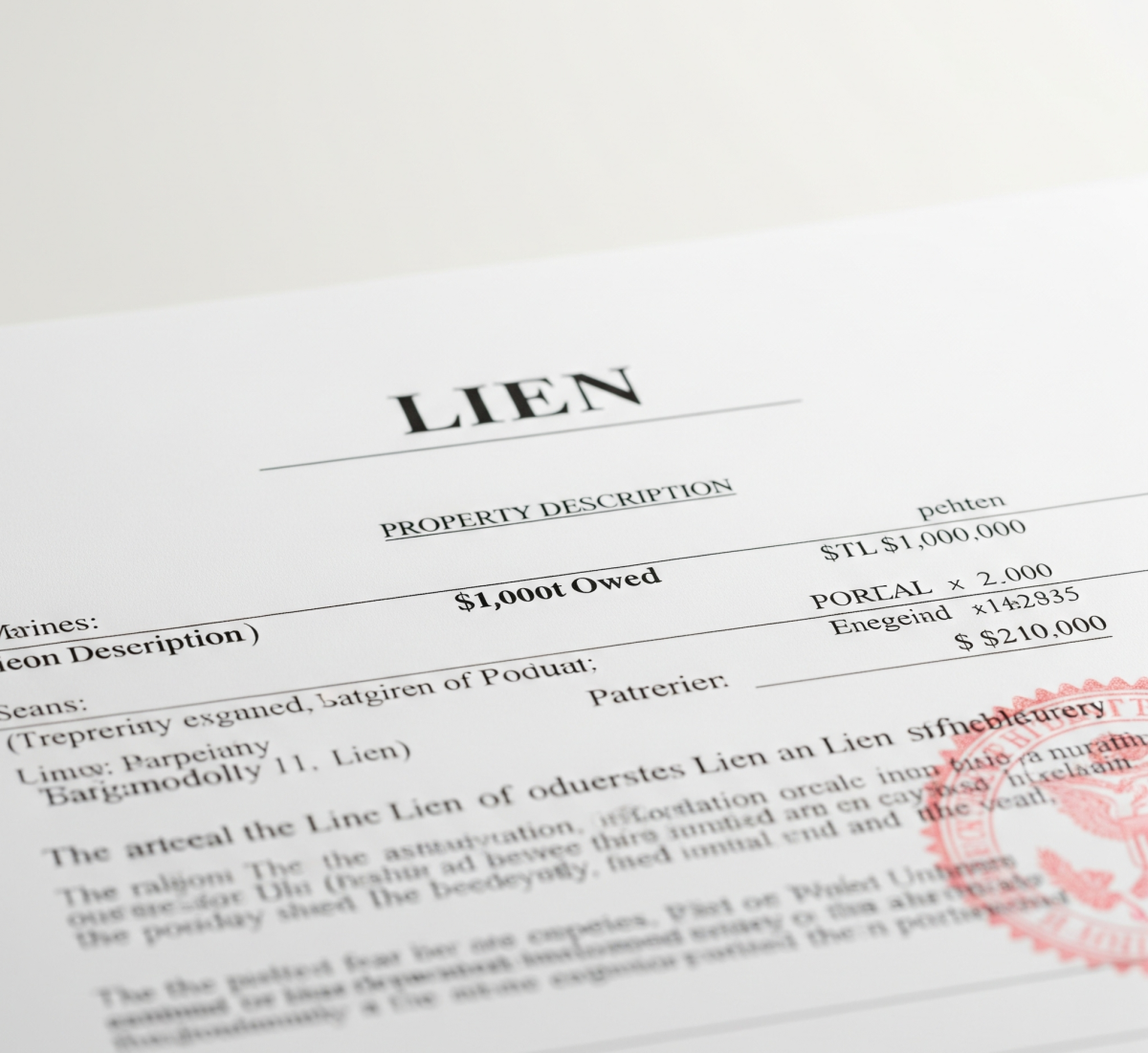こんにちは!
不動産を担保にしてお金を借りるとき、「抵当権」や「根抵当権」といった言葉を耳にすることがあります。どちらも「担保権」と呼ばれるもので、万が一借金を返せなくなった場合に、債権者が不動産を処分してお金を回収できる権利のことです。
しかし、この2つには大きな違いがあり、使われる場面やメリット・デメリットも異なります。この記事では、「抵当権」と「根抵当権」の違いを解説し、どのように使い分ければよいかを紹介します。
⚪︎抵当権とは? ──住宅ローンに使われる一般的な担保権
抵当権とは、特定の借金(=債権)に対して設定される担保権です。たとえば、住宅ローンを組んだとき、その家に抵当権が設定されるのが一般的です。借金を返済できなくなると、銀行などの債権者はその家を競売にかけ、そこから返済を受けることができます。
*抵当権の特徴
・特定の債務を担保
原則として、ひとつの借入契約(例:住宅ローン)を担保するためのものです。
・債務とセットで動く
借金を完済すれば抵当権も消えます(ただし、登記簿上は抹消登記が必要です)。
・順位が登記で決まる
複数の抵当権がある場合、登記された順番で優先順位が決まります。
*メリットとデメリット
・メリット
住宅ローンなどの明確な借入に適しており、手続きがシンプルです。
・デメリット
追加でお金を借りたい場合、その都度新たに抵当権を設定し直す必要があります。そのため、頻繁に借入や返済を繰り返す場面では不便です。
⚪︎根抵当権とは? ──事業資金など継続的な借入に向いた担保権
根抵当権は、将来的に発生するかもしれない複数の借金をまとめて担保にする権利です。特に事業者向けの融資や当座貸越(銀行と取引先が日常的にお金を出し入れするような契約)でよく利用されます。
*根抵当権の特徴
・不特定の債権を担保
借入のたびに設定し直す必要はなく、将来の借金も極度額の範囲内で自動的に担保されます。
・独立性がある
一度借金をゼロにしても、根抵当権はそのまま残り、再び借り入れをすることが可能です。
・極度額の設定
担保される借金の総額に上限(極度額)があり、その範囲内であれば何度でも借り入れが可能です。
・元本確定という考え方
あるタイミングで担保する範囲が確定し、それ以降の借金は対象外になります。
*メリットとデメリット
・メリット
繰り返しの借入・返済が想定される事業取引に最適。
何度借りても抵当権を設定し直す手間が不要で、手続きが効率的。
・デメリット
借金を完済しても自動で消えないため、抹消するには別途手続きが必要。
実際の借入額より高めに極度額を設定することが多く、不動産が過剰に担保される可能性もあります。
元本確定のタイミングが分かりづらく、トラブルの元になることも。
⚪︎それぞれの用途と比較
まとめると以下の通りになります。
①担保する債権
・抵当権…特定の一つの借入(住宅ローンなど)
・根抵当権…将来の複数の借入(事業資本)
②付従性
・抵当権…あり/借金の完済で消失
・根抵当権…なし/借金の完済で消失しない
③極度額の設定
・抵当権…なし
・根抵当権…あり
④融資のたびの手続き
・抵当権…毎回必要
・根抵当権…原則不要
⑤用途
・抵当権…住宅ローン、アパートローンなど
・根抵当権…事業性融資、当座貸越、手形取引など
不動産を担保にお金を借りる場合、抵当権と根抵当権の違いを理解することはとても重要です。
住宅ローンなど一度きりの借入には「抵当権」が適しています。手続きが明確で、完済すれば消えるシンプルな仕組みです。
対して、事業などで継続的に借入をするなら「根抵当権」の方が柔軟に対応できます。手続きの効率性と、急な資金需要への対応力が強みです。
どちらを選ぶべきかは、借入の目的や返済の計画によって変わります。金融機関や専門家とよく相談し、自分の状況に合った方法を選ぶようにしましょう。
不動産売買でのお悩みごとがありましたら、ぜひコンサルもできる弊社までお気軽にお問合せください!(^_−)−☆