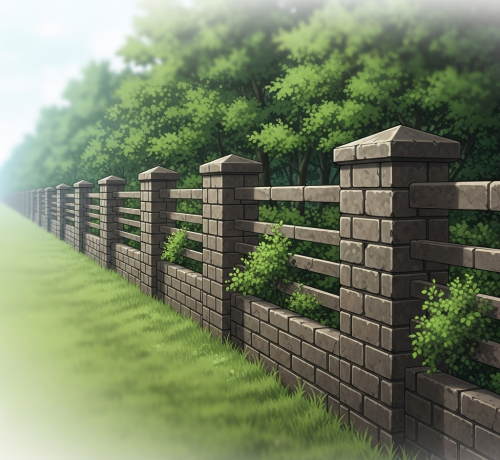こんにちは! 今回は「境界非明示(きょうかいひめいじ)」の土地がもたらすリスクと、その解決策についてお話ししていきますね。もしかしたら物件をお探しの方で、こちらの用語を見かけたことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。
土地の売買や相続、さらには隣人との関係において、土地の「境界」が明確であることは非常に重要です。しかし、すべての土地が明確な境界を持っているわけではありません。特に昔からの土地や市街地化されていない地域では、境界非明示(きょうかいひめいじ)と呼ばれる、境界が不明確な土地が多く存在します。
⚪︎境界非明示とは?
「境界非明示」とは、隣接する土地との境界線が現地で明確に示されていない状態のことを指します。たとえば、土地の境界を示す杭やプレートが設置されていなかったり、あっても位置がずれていたり、図面上でしか確認できないケースがこれに該当します。
ではどうしてこのようなケースが起きるのかと言いますと、
・古い登記制度の影響:明治時代に始まった日本の登記制度では、当時の測量技術や調査精度が不十分な地域も多く、登記情報が曖昧なまま残っています。
・測量未実施のままの取引:売買や相続の際に再測量をせず、昔のまま引き継がれてきた土地では境界が曖昧なままになっていることがあります。
・境界標の紛失や移動:自然災害や工事などで境界標が失われたり、誰かの意図で移動された可能性もあります。
・隣人同士の認識の違い:隣地の所有者と「この辺が境界だろう」という認識がずれていると、境界が不明確になります。
…といったことが考えられるでしょうか。
⚪︎あいまいな境界がもたらすリスク
1. 売却が難しくなる
土地を売ろうとする際、買い手はその土地の正確な範囲を知りたがります。境界がはっきりしないと、「トラブルの種」として敬遠され、売却価格が下がったり、取引そのものが成立しないこともあります。不動産業者も境界トラブルを避けるため、仲介に慎重になる傾向があります。
2. 隣人トラブルの原因に
最も起こりやすく、しかもやっかいなのが隣人とのトラブルです。
境界が曖昧だと、以下のような問題が発生します。
・越境トラブル:お互いの建物や塀、植栽が相手の敷地に越境していることが判明する。
・共有物の管理を巡る対立:塀や排水溝の所有や管理費を巡って言い争いになる。
・建築・開発の障害:境界が不明だと、建築確認申請が通らず、工事が進められない。
これらの問題が深刻化すれば、法的な紛争に発展し、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。
3. 土地の資産価値が下がる
境界が不明確な土地は、リスクが高いと見なされ、市場での評価が低くなります。将来的に売却する際も価格が上がりにくく、資産としての価値が目減りする可能性があります。
4. 相続がスムーズに進まない
境界がはっきりしない土地を相続する場合、分筆や売却などの手続きが難航します。相続人同士のトラブルに発展することも珍しくありません。
⚪︎境界問題の解決方法
境界非明示の土地は、放置せずに早めの対応が重要です。以下のような解決策があります。
1. 専門家による測量と境界標の設置
まずは土地家屋調査士に依頼して、現地の測量を実施しましょう。調査士は、古い図面や登記簿、隣地所有者の立ち会いなどをもとに、正確な境界を特定してくれます。そのうえで、境界標(杭など)を設置し、「境界確認書」を取り交わすことで、将来のトラブル防止になります。
2. 筆界特定制度の活用
隣人との合意が得られない場合は、法務局の筆界特定制度を利用できます。これは、土地の「所有権」ではなく「登記された境界」を公的に明らかにする制度です。裁判よりも手続きが簡単で、費用も比較的抑えられます。
3. 境界確定訴訟
どうしても合意できず、筆界特定制度でも解決しない場合は、裁判所に境界確定訴訟を提起することになります。最終的な法的判断が下されますが、時間や費用がかかり、隣人との関係も悪化するおそれがあるため、慎重に検討する必要があります。
4. 隣人との冷静な話し合い
最も大切なのは、隣人との信頼関係を維持しながら対話を進めることです。感情的にならず、昔の測量図や資料をもとに話し合い、必要があれば専門家にも同席してもらいましょう。
境界があいまいな土地は、思わぬトラブルを招き、資産価値にも悪影響を及ぼします。土地の売却や相続をスムーズに進めるためにも、境界を明確にしておくことは極めて重要です。
ご自身の土地に不安がある方、また境界が未確定の土地の購入を検討している方は、早めに専門家へ相談しましょう。測量や制度の活用を通じて、将来的なリスクを防ぎ、安心して土地を活用・継承できる体制を整えておくことが大切です。
収益不動産売買のご検討、管理・経営でお悩みごとがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください!(^_−)−☆